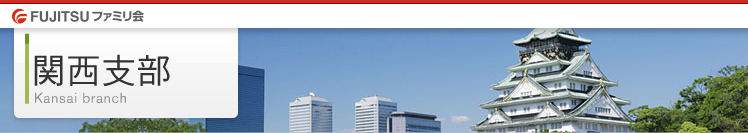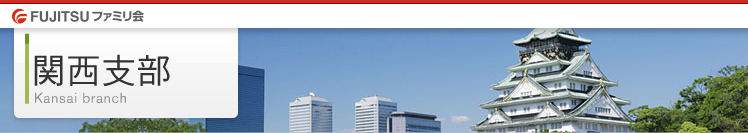| ●大物主(おおものぬし)が宿り、「箸墓伝説」とも深くかかわる三輪山 |
 三輪山(標高467m)には今も「大物主(おおものぬし)大神」が宿るという。大物主は、日本書紀や古事記に出てくる蛇体の神だ。出雲造神賀詞の「因幡(いなば)の白うさぎ」で有名な「大国主
(おおくにぬし)」と同神でもある。 三輪山(標高467m)には今も「大物主(おおものぬし)大神」が宿るという。大物主は、日本書紀や古事記に出てくる蛇体の神だ。出雲造神賀詞の「因幡(いなば)の白うさぎ」で有名な「大国主
(おおくにぬし)」と同神でもある。 |
 田辺さんによれば、三輪の語源として古事記にはこんな話があるそうだ。 田辺さんによれば、三輪の語源として古事記にはこんな話があるそうだ。 |
 「神代の昔、大和盆地に住んでいた活玉依毘売(いくたまよりひめ)が夜毎に通って来る男によって懐妊するのです。父母はその男の正体を知りたいと思って、糸巻きに巻いた麻糸を針に通し、針をその男の衣の裾に通すよう姫に教えます。翌朝、糸をたどると三輪山の社まで続き、大蛇がドクロを巻いていた・・・。男は山に住む大物主大神だったんです。糸巻きには糸が三勾(=三把)だけ残っていたのでこの山を"三輪"と呼んだのです」。 「神代の昔、大和盆地に住んでいた活玉依毘売(いくたまよりひめ)が夜毎に通って来る男によって懐妊するのです。父母はその男の正体を知りたいと思って、糸巻きに巻いた麻糸を針に通し、針をその男の衣の裾に通すよう姫に教えます。翌朝、糸をたどると三輪山の社まで続き、大蛇がドクロを巻いていた・・・。男は山に住む大物主大神だったんです。糸巻きには糸が三勾(=三把)だけ残っていたのでこの山を"三輪"と呼んだのです」。
|
 姫の名といい、その姫が見知らぬ男によって懐妊する筋書きといい、はて、どこかで聞いたことが・・・そう、先月号で紹介した上賀茂神社の伝説とそっくりではないか。 姫の名といい、その姫が見知らぬ男によって懐妊する筋書きといい、はて、どこかで聞いたことが・・・そう、先月号で紹介した上賀茂神社の伝説とそっくりではないか。
|
 一方、三輪山は、第十代崇神天皇の叔母で、巫女でもあった倭迹迹日百襲姫(やまとととひももそひめ)と大物主の神婚伝説でもある「箸墓伝説」とも深くかかわっている。 一方、三輪山は、第十代崇神天皇の叔母で、巫女でもあった倭迹迹日百襲姫(やまとととひももそひめ)と大物主の神婚伝説でもある「箸墓伝説」とも深くかかわっている。 |
 伝説では、百襲姫が、夜な夜な通ってきて日中は姿を見せない夫を不振に思い尋ねたところ、夫は「日中はお前の櫛箱の中に入っている」と答える。それで姫は朝のくるのを待って櫛箱をあけると、なんと中には美しい小蛇がいた。驚いた姫がショックで座り込んだところ、床にあった箸が陰処(ほと)に突き刺さって死んでしまう・・・。
伝説では、百襲姫が、夜な夜な通ってきて日中は姿を見せない夫を不振に思い尋ねたところ、夫は「日中はお前の櫛箱の中に入っている」と答える。それで姫は朝のくるのを待って櫛箱をあけると、なんと中には美しい小蛇がいた。驚いた姫がショックで座り込んだところ、床にあった箸が陰処(ほと)に突き刺さって死んでしまう・・・。
|
 その百襲姫の墓が、三輪山の北西にある箸墓(はしはか)古墳だという。箸墓は卑弥呼の墓という説もあるが、定かではない。
その百襲姫の墓が、三輪山の北西にある箸墓(はしはか)古墳だという。箸墓は卑弥呼の墓という説もあるが、定かではない。
|
 これらのことから、田辺さんは次のように解説する。
これらのことから、田辺さんは次のように解説する。 |
 「記紀などに書かれている話は、京都の賀茂社の伝説と同じく、この地が他者からの侵略を受けたことを表すものです。西方にある二上山では石器作りに欠かせない金剛砂やサヌカイトが採れたこともあり、この一体は古くから非常に魅力的な土地だったのでしょう。三輪山麓、山門を居所にした大和王権の人間が当地の神と通じることは、祭祀権を握ることであり、この地を征服したことを物語っています。ただ上賀茂では、侵略された人たちが和議の道を歩んだのに対して、この地の人たちは敵対し闘ったのではないでしょうか。私は箸墓伝説についても、大物主に抵抗した百襲姫が自害したと読み解いているんです」 「記紀などに書かれている話は、京都の賀茂社の伝説と同じく、この地が他者からの侵略を受けたことを表すものです。西方にある二上山では石器作りに欠かせない金剛砂やサヌカイトが採れたこともあり、この一体は古くから非常に魅力的な土地だったのでしょう。三輪山麓、山門を居所にした大和王権の人間が当地の神と通じることは、祭祀権を握ることであり、この地を征服したことを物語っています。ただ上賀茂では、侵略された人たちが和議の道を歩んだのに対して、この地の人たちは敵対し闘ったのではないでしょうか。私は箸墓伝説についても、大物主に抵抗した百襲姫が自害したと読み解いているんです」 |
 真実は、「三輪山のみぞ知る」ということかもしれない。血塗られた過去を封印するかのように三輪山は、いまも変わらぬ神秘的な姿で私たちを魅了する。 真実は、「三輪山のみぞ知る」ということかもしれない。血塗られた過去を封印するかのように三輪山は、いまも変わらぬ神秘的な姿で私たちを魅了する。 |
| |