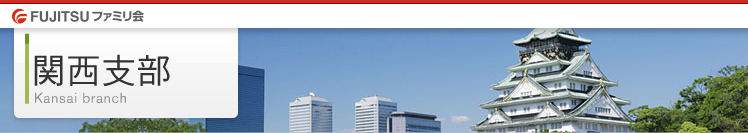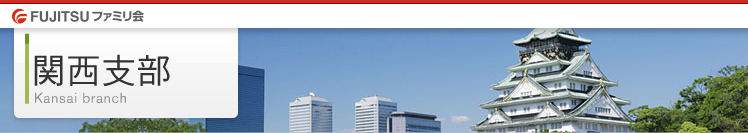| ●茶臼山と河底池に誕生の秘密 |
 茶臼山といえば大阪人なら知らない人はいないだろう。高さは10メートルばかり、港区にある天保山と合わせて山とも呼べないようなかわいい丘だ。もともと5世紀前半につくられた古墳であったとも言われている。また、慶長19年(1614年)大坂冬の陣では、一帯が徳川家康の本陣となり、翌年の大坂夏の陣では真田幸村の本陣となって「茶臼山の戦い」の舞台となった所としても知られる。 茶臼山といえば大阪人なら知らない人はいないだろう。高さは10メートルばかり、港区にある天保山と合わせて山とも呼べないようなかわいい丘だ。もともと5世紀前半につくられた古墳であったとも言われている。また、慶長19年(1614年)大坂冬の陣では、一帯が徳川家康の本陣となり、翌年の大坂夏の陣では真田幸村の本陣となって「茶臼山の戦い」の舞台となった所としても知られる。
|
 「河底池(こそこいけ・かわぞこいけ)」は、その茶臼山の南にある池だ。 「河底池(こそこいけ・かわぞこいけ)」は、その茶臼山の南にある池だ。 |
 西俣師匠が解説する。 西俣師匠が解説する。
|
 「この池は788年(延暦7年)、奈良時代の官僚、和気清麻呂(わけのきよまろ)が河内川(今の大和川)の水を大坂湾に引こうとしてつくった堀川の名残りなんやね」。 「この池は788年(延暦7年)、奈良時代の官僚、和気清麻呂(わけのきよまろ)が河内川(今の大和川)の水を大坂湾に引こうとしてつくった堀川の名残りなんやね」。
|
 なるほど、池に架かる赤い欄干の橋は「和気橋」という名だ。 なるほど、池に架かる赤い欄干の橋は「和気橋」という名だ。
|
 太古、上町台地と生駒山麓との間のこのあたりは、海の中だったという。 太古、上町台地と生駒山麓との間のこのあたりは、海の中だったという。
|
 「河内湖と言われる入江の湾で、それが長い長い時間をかけて徐々に土砂が堆積して陸地となったんやね。そのために河内平野は、低湿地で川の氾濫が多く、人々は度重なる大洪水に悩まされていたんや。
「河内湖と言われる入江の湾で、それが長い長い時間をかけて徐々に土砂が堆積して陸地となったんやね。そのために河内平野は、低湿地で川の氾濫が多く、人々は度重なる大洪水に悩まされていたんや。
|
 江戸時代の大和川の付け替えや安治川の開削、明治末期の新淀川の掘削、大正期の平野川の直線化工事も、みんな洪水対策のために行われたものなんや。大阪の歴史はそのまま水害との戦いやったといってもいい」。 江戸時代の大和川の付け替えや安治川の開削、明治末期の新淀川の掘削、大正期の平野川の直線化工事も、みんな洪水対策のために行われたものなんや。大阪の歴史はそのまま水害との戦いやったといってもいい」。
|
 奈良時代に和気清麻呂が行ったこの治水工事は、わが国における治水工事の草分けだったと推測される。 奈良時代に和気清麻呂が行ったこの治水工事は、わが国における治水工事の草分けだったと推測される。 |
 「工事には、延べ23万人もの人手を投入したと言われているんや。奈良時代の日本の人口は450万人。その中の23万人やから規模の大きさも半端やない。にもかかわらず工事は途中で失敗したらしい」と師匠はいう。 「工事には、延べ23万人もの人手を投入したと言われているんや。奈良時代の日本の人口は450万人。その中の23万人やから規模の大きさも半端やない。にもかかわらず工事は途中で失敗したらしい」と師匠はいう。 |
 和気清麻呂は、奈良時代から平安時代の転換期に活躍した官僚。桓武天皇の信任を得て近畿地方の河川改修や開削を行って治水に努めた。平安遷都が彼の立案であったことも有名だ。 和気清麻呂は、奈良時代から平安時代の転換期に活躍した官僚。桓武天皇の信任を得て近畿地方の河川改修や開削を行って治水に努めた。平安遷都が彼の立案であったことも有名だ。 |
 しかし、仏教政治が台頭する中、女帝、考謙天皇の寵愛を得て次第に権力の座に着こうとした僧・弓削道鏡の策略を阻止したことから、道鏡より手痛い仕返しを食らうことになる。「道鏡は、和気清麻呂の名前をもじって別部穢麻呂(わけのきたなまろ)に変えさせて大隈へ追放させたんやね、えげつない話」。これが後の世に語り継がれる「道鏡事件」だ。 しかし、仏教政治が台頭する中、女帝、考謙天皇の寵愛を得て次第に権力の座に着こうとした僧・弓削道鏡の策略を阻止したことから、道鏡より手痛い仕返しを食らうことになる。「道鏡は、和気清麻呂の名前をもじって別部穢麻呂(わけのきたなまろ)に変えさせて大隈へ追放させたんやね、えげつない話」。これが後の世に語り継がれる「道鏡事件」だ。 |
 一方、師匠はこんな説も披露する。 一方、師匠はこんな説も披露する。 |
 「茶臼山については5世紀後半頃の古墳であるとされる一方、上町台地を掘削した際に出た残土を積み上げた跡であるという学説もあるんや」。 「茶臼山については5世紀後半頃の古墳であるとされる一方、上町台地を掘削した際に出た残土を積み上げた跡であるという学説もあるんや」。 |
 もし、掘削工事の残土であるとすれば、茶臼山はもろに人々の汗と涙の結晶ではないか。 もし、掘削工事の残土であるとすれば、茶臼山はもろに人々の汗と涙の結晶ではないか。 |
 茶臼山と河底池は、天王寺公園の一角にある慶沢園から行けるが、公園の南側に隣接する「統国寺」の境内に立つと美しい絶景が臨める。統国寺は、第六話で紹介した「ベルリンの壁」のある朝鮮寺だ。<第六話へリンク> 茶臼山と河底池は、天王寺公園の一角にある慶沢園から行けるが、公園の南側に隣接する「統国寺」の境内に立つと美しい絶景が臨める。統国寺は、第六話で紹介した「ベルリンの壁」のある朝鮮寺だ。<第六話へリンク> |
|
●堀越町、河堀口・・・地名と道路のくぼ地に痕跡を残す治水工事 |
 「堀越町」「北河堀」「南河堀」「河堀口」など、地図を見れば、この治水工事に由来する町名が今も残る。この地名を手かがりに川筋をたどりつつ、界わいを散策しよう。 「堀越町」「北河堀」「南河堀」「河堀口」など、地図を見れば、この治水工事に由来する町名が今も残る。この地名を手かがりに川筋をたどりつつ、界わいを散策しよう。 |
 茶臼山のすぐ東、谷町筋の西側にある「堀越(ほりこし)神社」は、四天王寺建立と同時に創建されたという歴史ある神社だ。 茶臼山のすぐ東、谷町筋の西側にある「堀越(ほりこし)神社」は、四天王寺建立と同時に創建されたという歴史ある神社だ。 |
 治水工事は社記にも残り、神社の案内書には「昔より明治の中期まで、境内の南沿いに美しい堀があり、この堀を越えて参詣したので、堀越という名が付けられた」と記されている。神社の前で、何十台ものクルマが行き交う谷町筋を指差して声を張り上げた。 治水工事は社記にも残り、神社の案内書には「昔より明治の中期まで、境内の南沿いに美しい堀があり、この堀を越えて参詣したので、堀越という名が付けられた」と記されている。神社の前で、何十台ものクルマが行き交う谷町筋を指差して声を張り上げた。 |
 「ほら、この道!
上町台地は南へなだらかに低くなるのに、神社の前は大きくくぼんでいる。これこそ治水工事の堀川跡」。 「ほら、この道!
上町台地は南へなだらかに低くなるのに、神社の前は大きくくぼんでいる。これこそ治水工事の堀川跡」。 |
 見れば、南北に走る谷町筋の広い道路に対して垂直に、まるでU字の彫刻刀で筋を入れたかようななめらかなくぼみが続いている。 見れば、南北に走る谷町筋の広い道路に対して垂直に、まるでU字の彫刻刀で筋を入れたかようななめらかなくぼみが続いている。 |
| |
| ●庚申信仰のルーツがある四天王寺庚申堂 |
 谷町筋を渡って四天王寺の南側、堀越町の一角にある「四天王寺庚申堂」は、庚申信仰の発祥の地で、京都八坂、東京入谷(現存せず)と並ぶ日本三庚申の一つ。建立は大宝元年(701年)。 谷町筋を渡って四天王寺の南側、堀越町の一角にある「四天王寺庚申堂」は、庚申信仰の発祥の地で、京都八坂、東京入谷(現存せず)と並ぶ日本三庚申の一つ。建立は大宝元年(701年)。 |
| 「庚申(こうしん)」とは、干支で庚・申(かのえ・さる)の日のこと。中国の道教の言い伝えで、この前夜に人間の体の中にいる3匹の虫が寝ている間に体から抜け出して、神様にその人の行った悪行を告げ口に行くそうや。それを防ぐために庚申日の夜は寝んと徹夜するという風習があったんやね。まあ、この日は夜通で飲んでどんちゃん騒ぎをするわけや。酒飲みにはええ口実ができてたまらん楽しみやったんやろうね(笑)」 |
 師匠がなぜかうれしそうに話す。 師匠がなぜかうれしそうに話す。 |
 本尊の青面金剛童子は、この三匹の虫を食べると考えられていたので、いつの頃からか庚申日には、この仏様を拝む風習が広まっていったようだ。現在でも新年最初の庚申日には多くの参詣者で賑わう。 本尊の青面金剛童子は、この三匹の虫を食べると考えられていたので、いつの頃からか庚申日には、この仏様を拝む風習が広まっていったようだ。現在でも新年最初の庚申日には多くの参詣者で賑わう。 |
|
| ●歌舞伎、浄瑠璃の名手が眠る超願寺 |
 庚申堂の北にある超願寺は、義太夫節浄瑠璃の元祖といわれる竹本義太夫の菩提寺。
「竹本義太夫は、慶安4年(1651年)堀越神社の近くで生まれた。家は百姓やったけど、家の近くに料亭があってそこから聞こえてくる歌や三味線の音に魅かれて浄瑠璃を始めたんや」。 庚申堂の北にある超願寺は、義太夫節浄瑠璃の元祖といわれる竹本義太夫の菩提寺。
「竹本義太夫は、慶安4年(1651年)堀越神社の近くで生まれた。家は百姓やったけど、家の近くに料亭があってそこから聞こえてくる歌や三味線の音に魅かれて浄瑠璃を始めたんや」。
|
 研究熱心な義太夫は、浄瑠璃に当時の様々な歌いや語りの長所を採り入れ、『義太夫節』を完成させた。貞享元年(1684年)には道頓堀に「竹本座」を建設。近松門左衛門が座付作者となり始めたのが人形浄瑠璃である。「近松さんと並んで大阪の誇りやね」と、師匠。 研究熱心な義太夫は、浄瑠璃に当時の様々な歌いや語りの長所を採り入れ、『義太夫節』を完成させた。貞享元年(1684年)には道頓堀に「竹本座」を建設。近松門左衛門が座付作者となり始めたのが人形浄瑠璃である。「近松さんと並んで大阪の誇りやね」と、師匠。
|
 境内にある竹本義太夫の墓はお堂になっていて風雨から守られている。寺には他にも歌舞伎や浄瑠璃の関係者の墓が多くある。
境内にある竹本義太夫の墓はお堂になっていて風雨から守られている。寺には他にも歌舞伎や浄瑠璃の関係者の墓が多くある。
|
 また、堀越神社の南約100メートルの路上には『竹本義太夫生誕碑』が立っている。 また、堀越神社の南約100メートルの路上には『竹本義太夫生誕碑』が立っている。 |
|
|
|
●銭湯に親橋だけが残る「源ケ橋」 |
 この川筋は東へ進み、天王寺中学の前を通って、JR寺田町駅の高架をくぐり、源ケ橋の交差点あたりまで続く。 この川筋は東へ進み、天王寺中学の前を通って、JR寺田町駅の高架をくぐり、源ケ橋の交差点あたりまで続く。 |
 寺田町周辺は、かつて低湿地帯で猫間川を主な水源とする水田地帯だった。師匠が話す。
「寺田町の寺は、四天王寺のこと。そやから四天王寺さん専用の田んぼやね。寺で職務につく人たちが食べる米をつくっていたんや」。 寺田町周辺は、かつて低湿地帯で猫間川を主な水源とする水田地帯だった。師匠が話す。
「寺田町の寺は、四天王寺のこと。そやから四天王寺さん専用の田んぼやね。寺で職務につく人たちが食べる米をつくっていたんや」。
|
 源ケ橋は、かつてこの辺りを流れていた猫間川にかかっていた大きな橋だったが、川の埋め立てで姿を消した。川なき今は、寺田町駅前から続く「源ケ橋商店街」と「源ケ橋交差点」にその名を留めている。
源ケ橋は、かつてこの辺りを流れていた猫間川にかかっていた大きな橋だったが、川の埋め立てで姿を消した。川なき今は、寺田町駅前から続く「源ケ橋商店街」と「源ケ橋交差点」にその名を留めている。 |
 師匠によれば、地元では源ケ橋にまつわるこんな話が伝承されている。 師匠によれば、地元では源ケ橋にまつわるこんな話が伝承されている。 |
 「江戸時代に猫間川で渡し守をしている"源さん"という人がいたんやね。ものすごい悪で、通行人から金品をまきあげとったんや。ところがある日、一人の旅人からみぐるみ剥いで殺してしまったところ、よく見たら相手は長年行方知れずになっていた我が息子。それから深く悔やんだ源さん、有り金はたいて架けたのが源ケ橋というわけや」 「江戸時代に猫間川で渡し守をしている"源さん"という人がいたんやね。ものすごい悪で、通行人から金品をまきあげとったんや。ところがある日、一人の旅人からみぐるみ剥いで殺してしまったところ、よく見たら相手は長年行方知れずになっていた我が息子。それから深く悔やんだ源さん、有り金はたいて架けたのが源ケ橋というわけや」
|
 源ケ橋商店街には、「源ケ橋温泉」という銭湯がある。入浴とひっかけて屋根にニューヨークのシンボル自由の女神像がそびえている。その入口に、かつて猫間川に架かっていた源ケ橋の親柱が看板代わりに建っている。
源ケ橋商店街には、「源ケ橋温泉」という銭湯がある。入浴とひっかけて屋根にニューヨークのシンボル自由の女神像がそびえている。その入口に、かつて猫間川に架かっていた源ケ橋の親柱が看板代わりに建っている。
|

|
| ●治水工事のスタート地点だった「河堀口」
|
 川筋は、近鉄・南大阪線「河堀口(こぼれぐち)」の辺りでとだえている。師匠の解説。
川筋は、近鉄・南大阪線「河堀口(こぼれぐち)」の辺りでとだえている。師匠の解説。 |
 「河堀口は、河を掘る入口という意味。実はここが治水工事のスタート地点やったんやね。清麻呂は、このあたりから掘り始め、茶臼山の河底で、上町台地の岩盤に当たったか、資金が調達できなくなったかで挫折したんと違うやろうか。
"こぼれぐち"と読むのは、こぼりが訛ってこぼれになったんやね。松屋町を"まっちゃまち"、十三を"じゅうそう"と読むのと同じや」。
「河堀口は、河を掘る入口という意味。実はここが治水工事のスタート地点やったんやね。清麻呂は、このあたりから掘り始め、茶臼山の河底で、上町台地の岩盤に当たったか、資金が調達できなくなったかで挫折したんと違うやろうか。
"こぼれぐち"と読むのは、こぼりが訛ってこぼれになったんやね。松屋町を"まっちゃまち"、十三を"じゅうそう"と読むのと同じや」。
|