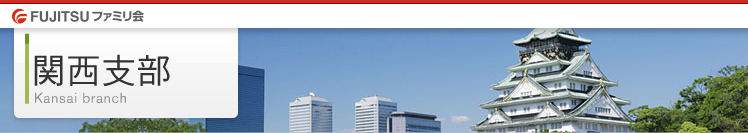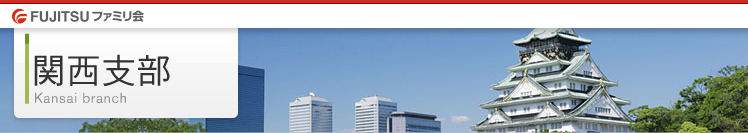| ●運河としてスタートした疏水 |
 琵琶湖疎水は、明治時代に琵琶湖の水を京都へ運ぶために作られた人工の水路。今では府民の水道用水として重要な水路だが、着工時は舟の運河としてスタートした。 琵琶湖疎水は、明治時代に琵琶湖の水を京都へ運ぶために作られた人工の水路。今では府民の水道用水として重要な水路だが、着工時は舟の運河としてスタートした。 |
 「明治維新で都が東京に移ったとき、京都の人はものすごく落ち込んだんです。このままでは経済と文化が衰退してしまう。そう考えた当時の知事、北垣国道が、京の町に元気を取り戻したいと計画したのが琵琶湖疎水開設事業やったんですね」 「明治維新で都が東京に移ったとき、京都の人はものすごく落ち込んだんです。このままでは経済と文化が衰退してしまう。そう考えた当時の知事、北垣国道が、京の町に元気を取り戻したいと計画したのが琵琶湖疎水開設事業やったんですね」
|
 当時、東海道への出入口、粟田口に至る山科と京都の間には逢坂山という急な坂道があるため陸路輸送は困難を極めたが、そこで考え出された水路開発計画だった。 当時、東海道への出入口、粟田口に至る山科と京都の間には逢坂山という急な坂道があるため陸路輸送は困難を極めたが、そこで考え出された水路開発計画だった。 |
 流路は、琵琶湖の南端、大津からスタートし、長等山ほか山科盆地の山麓をぶち抜いた3つのトンネルを通って京都市内を廻る。 流路は、琵琶湖の南端、大津からスタートし、長等山ほか山科盆地の山麓をぶち抜いた3つのトンネルを通って京都市内を廻る。
|
 「北垣知事は並み居るベテラン技師を起用せず、工部大学(今の東京大学)を卒業したばかりの21才の青年技師、田邊(たなべ)朔朗を抜擢したんです。そして彼を欧米に留学させ、世界の最新技術を学ばせた・・・」。 「北垣知事は並み居るベテラン技師を起用せず、工部大学(今の東京大学)を卒業したばかりの21才の青年技師、田邊(たなべ)朔朗を抜擢したんです。そして彼を欧米に留学させ、世界の最新技術を学ばせた・・・」。
|
 期待を受けた田邊技師は、水路と水路の高低差の大きい部分に「インクライン」と呼ばれる傾斜線路を敷き、船を線路の上の台車に載せて移動させるなどアイデアを駆使した。また、水路の水を使って発電、日本初の営業用水力発電所となる蹴上発電所を建設した。 期待を受けた田邊技師は、水路と水路の高低差の大きい部分に「インクライン」と呼ばれる傾斜線路を敷き、船を線路の上の台車に載せて移動させるなどアイデアを駆使した。また、水路の水を使って発電、日本初の営業用水力発電所となる蹴上発電所を建設した。
|
 1885年(明治18年)に着工した第1疏水(大津〜鴨川合流点間)は、1890年(明治23年)に完成。蹴上から分岐する疏水分線もこの時に完成した。工事には巨額の費用がかかったが、財源には京都府、国費、市債や寄付金のほか、産業基立金や市民からの特別な目的税が充てられた。続いて鴨川合流点から伏見までの鴨川運河が、1894年(明治27年)に完成。その後、1895年(明治28年)にはこの電力を用いて京都・伏見間で日本初となる路面電車「京都電気鉄道」の運転が開始され、京都のまちは一気に活気付いた。 1885年(明治18年)に着工した第1疏水(大津〜鴨川合流点間)は、1890年(明治23年)に完成。蹴上から分岐する疏水分線もこの時に完成した。工事には巨額の費用がかかったが、財源には京都府、国費、市債や寄付金のほか、産業基立金や市民からの特別な目的税が充てられた。続いて鴨川合流点から伏見までの鴨川運河が、1894年(明治27年)に完成。その後、1895年(明治28年)にはこの電力を用いて京都・伏見間で日本初となる路面電車「京都電気鉄道」の運転が開始され、京都のまちは一気に活気付いた。
|
|
●インクラインを歩く |
 そんな琵琶湖疏水の沿革を田辺さんから聞きながら、まず向ったのは、地下鉄東西線蹴上(けあげ)駅。駅の北側には、疏水掘削に伴って完成した水力発電所とインクラインがある。線路内には当時使われた貨車が残され、線路伝いに歩くことができる。 そんな琵琶湖疏水の沿革を田辺さんから聞きながら、まず向ったのは、地下鉄東西線蹴上(けあげ)駅。駅の北側には、疏水掘削に伴って完成した水力発電所とインクラインがある。線路内には当時使われた貨車が残され、線路伝いに歩くことができる。 |
 インクラインの下、蹴上浄水場から南禅寺の塔頭、金地院へ抜けるトンネルは、強度を考えてレンガをねじるような形で積んだことから「ねじりまんぽ」と呼ばれる。ちなみに「まんぽ」とはトンネルのこと。 インクラインの下、蹴上浄水場から南禅寺の塔頭、金地院へ抜けるトンネルは、強度を考えてレンガをねじるような形で積んだことから「ねじりまんぽ」と呼ばれる。ちなみに「まんぽ」とはトンネルのこと。 |
 「このレンガの積み方は独自のもの。疏水造作技術の高さが分ります」と田辺さん。 「このレンガの積み方は独自のもの。疏水造作技術の高さが分ります」と田辺さん。 |
 トンネルをぬけて南禅寺境内の山門をくぐり、東に進むとローマの水道橋のような建造物が現れる。これが「水路閣」。下から見ると分りにくいが、橋の上は水路になっていてゴーゴーと疏水が音を立てて流れている。 トンネルをぬけて南禅寺境内の山門をくぐり、東に進むとローマの水道橋のような建造物が現れる。これが「水路閣」。下から見ると分りにくいが、橋の上は水路になっていてゴーゴーと疏水が音を立てて流れている。 |
 疏水掘削工事を行う際、この界隈には社寺が多く点在していたため、環境や景観を壊さないような配慮がなされたという。異国風情緒漂うこの赤レンガの建造物は禅寺とも調和し、年月を経て独特の存在感を放っている。 疏水掘削工事を行う際、この界隈には社寺が多く点在していたため、環境や景観を壊さないような配慮がなされたという。異国風情緒漂うこの赤レンガの建造物は禅寺とも調和し、年月を経て独特の存在感を放っている。 |
| |
| ●平安神宮の神苑や御所の庭園の水も疏水 |
| 再び蹴上に戻り、今度は第一疏水の流路をたどってみる。疏水は仁王門通から平安神宮の前を通って一筋北の冷泉通に沿って流れ、そこから鴨川に注ぎ込む。 |
| 平安神宮の神苑の水も疏水の水だ。神宮道に架かる朱塗りの慶流橋の辺りは、疏水の美しさを引き立てる華やかな場所だ。 |
| 冷泉通沿いの疏水の途中には夷川発電所がある。「この夷川発電所の貯水池は、京都踏水会がプール代わりに使っていたこともあるんですよ」。京都踏水会は、明治時代に大日本武徳会遊泳部としてスタートした名門の水泳クラブ。1928年(昭和3年)アムステルダムオリンピックに出場した新井・木村両選手をはじめ、多くのスター選手を輩出している。 |
| 鴨川の東側と合流する地点は、俗に「中落」と呼ばれるところでダムになっている。
「ぼくが子供の頃はここでよく泳いだものです」。 田辺さんが懐かしそうに話す。 |
|
| ●桜の似合う哲学の道 |
 一方、蹴上から分かれた疏水分線は、南禅寺の境内で水路閣をまたいで「松ヶ崎浄水場」へと流れ、その後下鴨から堀川に達する。観光名所として知られる「哲学の道」は、松ヶ崎浄水場へ注ぐ途中、熊野若王子(くまのにゃくおうじ)神社から銀閣寺付近までの疏水分線の堤の遊歩道だ。 一方、蹴上から分かれた疏水分線は、南禅寺の境内で水路閣をまたいで「松ヶ崎浄水場」へと流れ、その後下鴨から堀川に達する。観光名所として知られる「哲学の道」は、松ヶ崎浄水場へ注ぐ途中、熊野若王子(くまのにゃくおうじ)神社から銀閣寺付近までの疏水分線の堤の遊歩道だ。 |
 哲学の道へは南禅寺を経由しても行けるが、私たちはクルマで銀閣寺前へ。 哲学の道へは南禅寺を経由しても行けるが、私たちはクルマで銀閣寺前へ。 |
 哲学の道というネーミングは、明治初期この当たりに下宿していた京都大学の学生たちが西ドイツにある「哲学者の道」にちなんで命名したとか。 哲学の道というネーミングは、明治初期この当たりに下宿していた京都大学の学生たちが西ドイツにある「哲学者の道」にちなんで命名したとか。 |
 疏水べりの木々は桜の木。この時期、赤や黄色に染まった落ち葉がキラリと舞って透明の川面を流れていくさまは、本当に美しい。 疏水べりの木々は桜の木。この時期、赤や黄色に染まった落ち葉がキラリと舞って透明の川面を流れていくさまは、本当に美しい。
|
 しかし、田辺さんは疏水には秋よりも春が似合うという。 しかし、田辺さんは疏水には秋よりも春が似合うという。 |
 そのわけは、銀閣寺近くにある白沙村荘(はくさそんそう)に由来する。白沙村荘は日本画家の巨匠、橋本関雪の自宅兼アトリエ。主亡きいまは記念館になっている。 そのわけは、銀閣寺近くにある白沙村荘(はくさそんそう)に由来する。白沙村荘は日本画家の巨匠、橋本関雪の自宅兼アトリエ。主亡きいまは記念館になっている。
|
| 「疏水の桜は関雪の夫人の米子さんが、夫の成功を祝って100本のソメイヨシノを植樹したのが始まりなんです。疏水ベリに桜が多いのもここから広がったんですね。私も疏水の桜は大好きで中学生の頃からカメラをぶら下げては歩いたものです」。
|
|
|