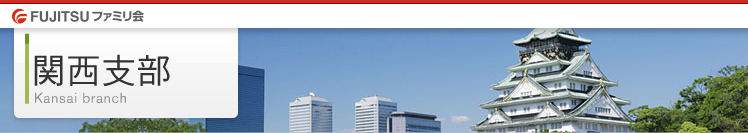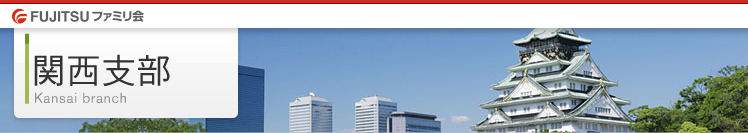| ●道を隔てて古い寺町と新しい寺町が対比的に並ぶ谷町筋のナゾ |
 今回、谷町筋を南下する師匠が手にするのは、天保時代の古地図。 今回、谷町筋を南下する師匠が手にするのは、天保時代の古地図。 |
 「たとえばここ、妙法寺は古地図にもあるね。天保時代から連綿と続いている寺がいっぱいあることに注目して」と師匠。 「たとえばここ、妙法寺は古地図にもあるね。天保時代から連綿と続いている寺がいっぱいあることに注目して」と師匠。
|
 もう一つは、寺の建物。「谷町筋に面してこちらの東側の寺は土塀で古い建物なのに、道路を隔てた西側の寺は近代的なコンクリートやね。なぜか。江戸時代の谷町筋の道幅は6メートルやったけど、万博のあった昭和45年に拡幅したんや。その際に西側の寺は立退いて新築移転したんやね」。 もう一つは、寺の建物。「谷町筋に面してこちらの東側の寺は土塀で古い建物なのに、道路を隔てた西側の寺は近代的なコンクリートやね。なぜか。江戸時代の谷町筋の道幅は6メートルやったけど、万博のあった昭和45年に拡幅したんや。その際に西側の寺は立退いて新築移転したんやね」。 |
 こんなところにも谷町筋の歴史が読み取れる。 こんなところにも谷町筋の歴史が読み取れる。
|
 谷町7丁目の交差点を東に曲がると、突然道のど真ん中に立派なクスノキが立っている。この場所にあった本照寺が通りの拡幅で立ち退いた際に、御神木を切ると縁起が悪いというのでクスノキだけが残ったという。ちなみに東西に伸びるこの「楠通り」は、昭和初期に軍用道路として計画されたもの。「大阪城公園にあった砲兵工場から、今ミナミにあるアメリカ村や、九条商店街、今も残る安治川川底トンネルを通って、桜島まで一本でつながる予定やったんです。アジアの戦地へ兵器を運ぶためにね」。 谷町7丁目の交差点を東に曲がると、突然道のど真ん中に立派なクスノキが立っている。この場所にあった本照寺が通りの拡幅で立ち退いた際に、御神木を切ると縁起が悪いというのでクスノキだけが残ったという。ちなみに東西に伸びるこの「楠通り」は、昭和初期に軍用道路として計画されたもの。「大阪城公園にあった砲兵工場から、今ミナミにあるアメリカ村や、九条商店街、今も残る安治川川底トンネルを通って、桜島まで一本でつながる予定やったんです。アジアの戦地へ兵器を運ぶためにね」。
|
 しかし、完成を間近にして終戦。幸いなことに、この道は一度も軍用トラックが走ることなかったという。一本の道が、あらためて平和というものについて考えさせてくれる。 しかし、完成を間近にして終戦。幸いなことに、この道は一度も軍用トラックが走ることなかったという。一本の道が、あらためて平和というものについて考えさせてくれる。
|
|
|
 谷町筋を南に進むと「曾根崎心中」や「心中天網島」で知られる近松門左衛門の墓がある。ただし、墓はガソリンスタンドとマンションの間の路地ともいえないような隙間の奥に。よほど注意しないと見落としてしまう。路地の入口に手書きの案内札が貼られているが、本当にお粗末。「何やねん。日本のシェークスピアともいえる大作家をこんな狭いところに閉じ込めて。尼崎市には近松の功績をたたえる記念館があるというのに。大阪の文化行政の貧しさを感じる」と憤慨する師匠。確かにこれでは同じ大阪人として恥ずかしい気がする。なんとかならないものだろうか。 谷町筋を南に進むと「曾根崎心中」や「心中天網島」で知られる近松門左衛門の墓がある。ただし、墓はガソリンスタンドとマンションの間の路地ともいえないような隙間の奥に。よほど注意しないと見落としてしまう。路地の入口に手書きの案内札が貼られているが、本当にお粗末。「何やねん。日本のシェークスピアともいえる大作家をこんな狭いところに閉じ込めて。尼崎市には近松の功績をたたえる記念館があるというのに。大阪の文化行政の貧しさを感じる」と憤慨する師匠。確かにこれでは同じ大阪人として恥ずかしい気がする。なんとかならないものだろうか。 |
|
●谷町界隈寺と坂が多いわけは |
 谷町筋の西側を渡り「地蔵坂」と呼ばれる急な坂を下ると、その名も「中寺」という寺町が広がる。ところで、谷町界隈には寺が多いのはどうして? 谷町筋の西側を渡り「地蔵坂」と呼ばれる急な坂を下ると、その名も「中寺」という寺町が広がる。ところで、谷町界隈には寺が多いのはどうして? |
 「豊臣秀吉の防衛戦略やったんやね。大坂城を取り囲んで北は大川、西は東横堀川、東は猫間川や大和川があるけど、南は防衛が弱い。それで上町台地の岩盤地形を利用しつつ寺を固めて防衛柵にしようと。とくに南にある下寺町には、26もの寺がぎっしり並んでいてネズミも通れないほど。これぞ秀吉の時代から踏襲された寺町の姿なんや」。 「豊臣秀吉の防衛戦略やったんやね。大坂城を取り囲んで北は大川、西は東横堀川、東は猫間川や大和川があるけど、南は防衛が弱い。それで上町台地の岩盤地形を利用しつつ寺を固めて防衛柵にしようと。とくに南にある下寺町には、26もの寺がぎっしり並んでいてネズミも通れないほど。これぞ秀吉の時代から踏襲された寺町の姿なんや」。
|
 また、この辺りは寺と同時に坂が多い。これについて師匠は、次のように説明する。 また、この辺りは寺と同時に坂が多い。これについて師匠は、次のように説明する。
|
 「古代の地形そのままやねん。大昔は大阪湾が今の御堂筋あたりまで繰り出し、岩盤だった上町台地から海岸線に下る地形が坂になったというわけや」。 「古代の地形そのままやねん。大昔は大阪湾が今の御堂筋あたりまで繰り出し、岩盤だった上町台地から海岸線に下る地形が坂になったというわけや」。
|
 この後に巡る「天王寺七坂」は、そんな坂の中でもとりわけ風情ある坂が人知れず伝えられ、隠れた名所にもなっている。 この後に巡る「天王寺七坂」は、そんな坂の中でもとりわけ風情ある坂が人知れず伝えられ、隠れた名所にもなっている。
|
|
| ●「縁切坂」も「相合坂」もある高津宮。恋の道は昔も今も・・・ |
 中寺の南方、一段高い丘の上にある高津宮は、仁徳天皇ゆかりの神社だ。境内には絵馬堂という舞台があり市内が一望できる。かつてここからナニワのまちを眺め、かまどに煙が上がらないことに気付いた仁徳天皇は、貧しい民の暮らしを案じ、税金免除したという話が伝えられている。仁徳天皇については、昨今実在するか否かが議論されるが、
「それは学者にお任せするとして」。 中寺の南方、一段高い丘の上にある高津宮は、仁徳天皇ゆかりの神社だ。境内には絵馬堂という舞台があり市内が一望できる。かつてここからナニワのまちを眺め、かまどに煙が上がらないことに気付いた仁徳天皇は、貧しい民の暮らしを案じ、税金免除したという話が伝えられている。仁徳天皇については、昨今実在するか否かが議論されるが、
「それは学者にお任せするとして」。 |
| 師匠が注目するのは、参道にある小さな石の反り橋だ。この橋は「梅乃橋」と言い、かつてはその下を「梅川」が流れていたという。師匠によれば「上町台地は、昔から水が湧くところとして知られているけど、この川の水源もその湧き水やったんやね。梅川は上町台地を西に流れ、なんと道頓堀の源流とも言われている」というから驚き!
|
|
|
 いっぽう、高津宮には境内に通じる四ヵ所の階段があるが、西の階段は、明治時代中期まで三下りと半分の坂だったため、離縁状を意味する「三行半(みくだりはん)」にからめて「縁切坂」と呼ばれていたとか。そこで、明治中期、神社では一策を講じ、新たに左右、2つの石畳の階段を設け、上で落ち合うようにしたという。こちらは「相合坂(あいあいざか)」と呼ばれている。いかにもダジャレ好きの大阪人のセンスがしのばれる粋なネーミングだ。 いっぽう、高津宮には境内に通じる四ヵ所の階段があるが、西の階段は、明治時代中期まで三下りと半分の坂だったため、離縁状を意味する「三行半(みくだりはん)」にからめて「縁切坂」と呼ばれていたとか。そこで、明治中期、神社では一策を講じ、新たに左右、2つの石畳の階段を設け、上で落ち合うようにしたという。こちらは「相合坂(あいあいざか)」と呼ばれている。いかにもダジャレ好きの大阪人のセンスがしのばれる粋なネーミングだ。
|
| |