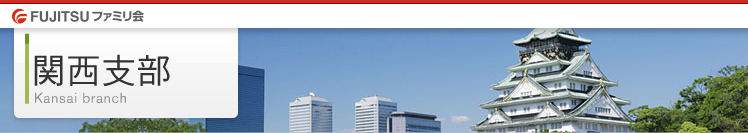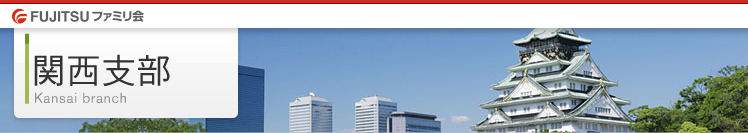| ●百済人が開墾した「百済野」と、ウグイス飛び交うかつての桃畑を歩く |
 近鉄上六駅から鶴橋へは、東へ一駅。しかし師匠は、まっすぐ東へは進まず、出口を出て、環状線桃谷駅のある東南方向に。 近鉄上六駅から鶴橋へは、東へ一駅。しかし師匠は、まっすぐ東へは進まず、出口を出て、環状線桃谷駅のある東南方向に。 |
 「この傾斜を歩くと、上町台地から下っていく地形がよく分るねん。それとこの辺りは、百済野(くだらの)と呼ばれていたんや。660年に朝鮮半島で新羅に滅ぼされた百済人がたくさん渡ってきてここを開墾したんやね。農業、漢字、土木技術、陶工、いろんな先進技術を持ってな。奈良から平安時代にかけては百済郡が置かれたし、平野川も百済川と呼ばれていた。百済という地名はもうないけど、百済貨物駅、南百済小学校、百済大橋・・・名前は残っている」。 「この傾斜を歩くと、上町台地から下っていく地形がよく分るねん。それとこの辺りは、百済野(くだらの)と呼ばれていたんや。660年に朝鮮半島で新羅に滅ぼされた百済人がたくさん渡ってきてここを開墾したんやね。農業、漢字、土木技術、陶工、いろんな先進技術を持ってな。奈良から平安時代にかけては百済郡が置かれたし、平野川も百済川と呼ばれていた。百済という地名はもうないけど、百済貨物駅、南百済小学校、百済大橋・・・名前は残っている」。
|
 へ〜、それは初耳。上本町からスタートしたのはそんな理由があったんだ。 へ〜、それは初耳。上本町からスタートしたのはそんな理由があったんだ。 |
 見れば「細工谷(さいくだに)」という名の交差点に。この辺りは細工谷という町名が付いている。師匠によれば「地形が起伏に富んで人が細工したようにきれいやったから」。 見れば「細工谷(さいくだに)」という名の交差点に。この辺りは細工谷という町名が付いている。師匠によれば「地形が起伏に富んで人が細工したようにきれいやったから」。
|
 でも、周辺はなだらかで、とてもそんな風には見えないけど・・・。首をかしげながら師匠の後を追うと、細い路地を通り抜けてちょっとした高台に。見下ろすと緑に覆われた段々畑のような空き地が現れ、地名をしのばせる地形が感じ取れる。 でも、周辺はなだらかで、とてもそんな風には見えないけど・・・。首をかしげながら師匠の後を追うと、細い路地を通り抜けてちょっとした高台に。見下ろすと緑に覆われた段々畑のような空き地が現れ、地名をしのばせる地形が感じ取れる。
|
 交差点近く、聖バルナバ病院前の地蔵尊のフェンスには「細工谷遺跡へようこそ」と書かれた説明板も。写真付きで「ここからは百済尼寺の土器が出土し、和同開珎が発見された」とあるが、説明板は雨ざらしになって風化がはなはだしい。いつもながら、大阪市の文化財の扱いに憤りを覚える。 交差点近く、聖バルナバ病院前の地蔵尊のフェンスには「細工谷遺跡へようこそ」と書かれた説明板も。写真付きで「ここからは百済尼寺の土器が出土し、和同開珎が発見された」とあるが、説明板は雨ざらしになって風化がはなはだしい。いつもながら、大阪市の文化財の扱いに憤りを覚える。
|
 上町台地東傾斜面は、明治時代まであたり一面、桃畑でもあったという。確かに南側には「桃谷」の地名があるし、キョロキョロ見回すと桃づくし。清風学園前の陸橋は「桃丘歩道橋」だし、「桃陽電線株式会社」の看板や「桃陽こども広場」も・・・。 上町台地東傾斜面は、明治時代まであたり一面、桃畑でもあったという。確かに南側には「桃谷」の地名があるし、キョロキョロ見回すと桃づくし。清風学園前の陸橋は「桃丘歩道橋」だし、「桃陽電線株式会社」の看板や「桃陽こども広場」も・・・。
|
 「桃谷」は、もともと「桃山」と呼ばれていたが、畑が細長く広がっているため美称として「谷」を用いたとか。環状線桃谷駅も、明治28年の開業当初は城東線「桃山駅」だったが、奈良線の桃山駅と混同するため明治38年に改称されたという。 「桃谷」は、もともと「桃山」と呼ばれていたが、畑が細長く広がっているため美称として「谷」を用いたとか。環状線桃谷駅も、明治28年の開業当初は城東線「桃山駅」だったが、奈良線の桃山駅と混同するため明治38年に改称されたという。
|
 細工谷の路地の脇に「是ヨリ西南鶯の丘」の碑がひっそり建っている。 細工谷の路地の脇に「是ヨリ西南鶯の丘」の碑がひっそり建っている。
|
 「桃畑やからウグイスが来た。カラスも来た。なんでか。この南には烏ヶ辻という地名もある(笑)」と師匠。今からは想像もつかないのどかな光景。 「桃畑やからウグイスが来た。カラスも来た。なんでか。この南には烏ヶ辻という地名もある(笑)」と師匠。今からは想像もつかないのどかな光景。
|
|
●シャッター1枚にも込められた歴史。生きるパワーみなぎる国際マーケット |
 鶴橋駅の高架下には、迷路のように延びるアーケード街が広がる。ここ国際マーケットは、約14万人という生野区の人口4分の1を占める在日コリアンの胃袋を支える台所でも。幅2mほどの道の両側には真っ赤なキムチや、カラフルな民族衣装を売る店が、所狭しとひしめき合っている。店頭に並ぶお惣菜の色香に心を奪われていると「この幅に注目して」と師匠が、シャッターの下りた店の前で両手を広げて立ち止まった。 鶴橋駅の高架下には、迷路のように延びるアーケード街が広がる。ここ国際マーケットは、約14万人という生野区の人口4分の1を占める在日コリアンの胃袋を支える台所でも。幅2mほどの道の両側には真っ赤なキムチや、カラフルな民族衣装を売る店が、所狭しとひしめき合っている。店頭に並ぶお惣菜の色香に心を奪われていると「この幅に注目して」と師匠が、シャッターの下りた店の前で両手を広げて立ち止まった。 |
 「1間180センチ、これが大事なんや。戦後闇市の跡が陣取り合戦になったときに、日本に渡ってきたオモニたちが警察の弾圧にも屈せず、絶対に渡すまいとバラックを立てて守り抜いた、その寝床のスペースなんやね。この幅に歴史の足跡がある」。 「1間180センチ、これが大事なんや。戦後闇市の跡が陣取り合戦になったときに、日本に渡ってきたオモニたちが警察の弾圧にも屈せず、絶対に渡すまいとバラックを立てて守り抜いた、その寝床のスペースなんやね。この幅に歴史の足跡がある」。 |
 マーケットを通り抜けると、道幅の広い鶴橋本通に出る。 マーケットを通り抜けると、道幅の広い鶴橋本通に出る。
|
 そこで師匠がまた1軒の建物を指差した。見れば、香港映画に出てくる九龍城みたいな恐ろしく古びた建物。レンガ塀に取り囲まれ、中庭にも家が増築されている。 そこで師匠がまた1軒の建物を指差した。見れば、香港映画に出てくる九龍城みたいな恐ろしく古びた建物。レンガ塀に取り囲まれ、中庭にも家が増築されている。 |
 「キョンチャルアパート、地元の人はこう呼んではる。1年ほど前からもう誰も住んでいないけど。キョンチャルとはハングルで警察。つまり警察アパートやな。なんでこんな名前がついてのか、誰に聞いても分らへん。ところが」。 「キョンチャルアパート、地元の人はこう呼んではる。1年ほど前からもう誰も住んでいないけど。キョンチャルとはハングルで警察。つまり警察アパートやな。なんでこんな名前がついてのか、誰に聞いても分らへん。ところが」。
|
| 師匠がおもむろに鞄から取り出したのは、大正14年に作られた古地図。 |
| 「ここに載っていたんやね。なんと戦前まで鶴橋警察やった」。 |
| いつからかは定かではないが、警察跡に人々が住み始め、民間アパートになったという。築100年以上のアパートの正式名称は「新共栄荘」。間口は狭いが、奥行きが長く、2階建ての建物の中には、なんと4畳半と10畳の部屋が55室も! これは、取材に同行させてもらった毎日新聞・松井宏員記者のその後の取材成果だ。 |
| 「動乱期を生き抜いてきた人たちのパワーを感じる」と師匠。近く取り壊されるそうだが、激動の時代の生き証人のようなこの建物に、思わず"お疲れ様でした!"と頭を下げた |
|
| ●今はなき旧平野川を挟んで栄えた、木野村と猪飼野村 |
 鶴橋本通の商店街を突きぬけ車道を越えると、辺りは一転して白壁板塀の民家が連なる和風情緒漂う街並みに。 鶴橋本通の商店街を突きぬけ車道を越えると、辺りは一転して白壁板塀の民家が連なる和風情緒漂う街並みに。 |
 師匠が手にする明治時代の地図によれば、ここは東成郡「木野村(このむら)」と呼ばれたところ。川をはさんですぐ横に「猪飼野村(いかいのむら)」が控えている。猪飼野の地名は、昭和48年の町名変更で消されたが、もともとイノシシを飼育する猪飼部が住む地という由緒ある地名で、日本書紀にも記されている「猪甘津(いかいつ)」がルーツ。 師匠が手にする明治時代の地図によれば、ここは東成郡「木野村(このむら)」と呼ばれたところ。川をはさんですぐ横に「猪飼野村(いかいのむら)」が控えている。猪飼野の地名は、昭和48年の町名変更で消されたが、もともとイノシシを飼育する猪飼部が住む地という由緒ある地名で、日本書紀にも記されている「猪甘津(いかいつ)」がルーツ。 |
 「明治時代には、まだまだ在日コリアンは少なかった。ところが旧平野川はくねくねと蛇行して何度も洪水があったために、大正8年(1919年)から新しい川が開削されたんや。それが今の平野川。明治43年(1910年)から始まった日韓併合という名の朝鮮半島支配とあいまって、この工事に多くのコリアンが半島からやってきて日本人の半分の賃金で過酷な労働に就いたんや。生野区に在日コリアンが爆発的に増えた理由の一つに、このことがある」。 「明治時代には、まだまだ在日コリアンは少なかった。ところが旧平野川はくねくねと蛇行して何度も洪水があったために、大正8年(1919年)から新しい川が開削されたんや。それが今の平野川。明治43年(1910年)から始まった日韓併合という名の朝鮮半島支配とあいまって、この工事に多くのコリアンが半島からやってきて日本人の半分の賃金で過酷な労働に就いたんや。生野区に在日コリアンが爆発的に増えた理由の一つに、このことがある」。 |
 いま私たちが享受している平和で安全で豊かな暮らし。この時代の後ろにあるものに、私たちはもっと目を向けなければいけない。 いま私たちが享受している平和で安全で豊かな暮らし。この時代の後ろにあるものに、私たちはもっと目を向けなければいけない。
|
 かいわいには二つの神社がある。旧木野村の氏神「弥栄(やえ)神社」と、旧猪飼野村の氏神「御幸森(みゆきのもり)天神社」だ。明治以降、村に神社は一つと定められたにもかかわらず二つあるのは、今はなき旧平野川をはさんで二つの村があった証しでもある。 かいわいには二つの神社がある。旧木野村の氏神「弥栄(やえ)神社」と、旧猪飼野村の氏神「御幸森(みゆきのもり)天神社」だ。明治以降、村に神社は一つと定められたにもかかわらず二つあるのは、今はなき旧平野川をはさんで二つの村があった証しでもある。
|
 御幸森天神社に掲げられた略記には、「仁徳天皇は鷹狩の折、我国に渡来し先進文化を伝えた百済の人々の状態をご見聞になる道すがら度々当地の森でご休憩された」とある。 御幸森天神社に掲げられた略記には、「仁徳天皇は鷹狩の折、我国に渡来し先進文化を伝えた百済の人々の状態をご見聞になる道すがら度々当地の森でご休憩された」とある。
|
| 「仁徳天皇の存在については議論されるけど、先進技術を伝えた百済の人々に対して敬意の念をもたれたと神社の歴史に記されているわけや。すばらしいことやね」と師匠。
|
|
|
|
●新しいパワーがみなぎるコリアンタウンと、鶴橋のルーツ・猪飼野新橋 |
 お目当てのコリアンタウンは、その御幸森天神社のすぐ東から平野川に向って伸びる商店街。正式名称は「御幸通商店街」。長年「朝鮮市場」として地元コリアンたちの間でにぎわっていたが、平成5年に商店街の人たちが団結して通りを整備し、入口に百済門と中央門などシンボルゲートなどを新設、国際色豊かな新しいまちに蘇った。 お目当てのコリアンタウンは、その御幸森天神社のすぐ東から平野川に向って伸びる商店街。正式名称は「御幸通商店街」。長年「朝鮮市場」として地元コリアンたちの間でにぎわっていたが、平成5年に商店街の人たちが団結して通りを整備し、入口に百済門と中央門などシンボルゲートなどを新設、国際色豊かな新しいまちに蘇った。 |
 平野川には、今はなき猪飼野の地名が付けられた「猪飼野新橋」が架かっている。親柱には前方後円墳や勾玉がデザインされ、欄干には日本書紀にある「猪甘津に橋為(わた)す 即ち其の処を号(なづ)けて小橋と曰う也」にちなむ漢字がシンボル的に配置されている。 平野川には、今はなき猪飼野の地名が付けられた「猪飼野新橋」が架かっている。親柱には前方後円墳や勾玉がデザインされ、欄干には日本書紀にある「猪甘津に橋為(わた)す 即ち其の処を号(なづ)けて小橋と曰う也」にちなむ漢字がシンボル的に配置されている。
|
 「日本書紀にある猪甘津にかかる橋というのは、西暦323年に百済川に架けられた日本最古の橋といわれ、実はこれぞ鶴橋のルーツ。その後、鶴が多く飛来したので鶴橋の名になったといわれているや」。 「日本書紀にある猪甘津にかかる橋というのは、西暦323年に百済川に架けられた日本最古の橋といわれ、実はこれぞ鶴橋のルーツ。その後、鶴が多く飛来したので鶴橋の名になったといわれているや」。 |
 猪飼野新橋の北西、疎開道路に抜ける細い道には「七福の辻」の碑がある。 猪飼野新橋の北西、疎開道路に抜ける細い道には「七福の辻」の碑がある。
|
 「ここは大正初めに道路が新設されて六辻になって当初"六道の辻"と呼ばれたんや。六道は死後の六道輪廻(地獄道、餓鬼道、畜生道、修羅道、人間道、天道)の分かれ道で、その一本が鶴橋斎場に通じて墓道と呼ばれたこともあってね。けど六道では縁起が悪いんで、地元の有力者がもう1本の細い路地を加えて"七福の辻"に改めたんや。すごい知恵」。 「ここは大正初めに道路が新設されて六辻になって当初"六道の辻"と呼ばれたんや。六道は死後の六道輪廻(地獄道、餓鬼道、畜生道、修羅道、人間道、天道)の分かれ道で、その一本が鶴橋斎場に通じて墓道と呼ばれたこともあってね。けど六道では縁起が悪いんで、地元の有力者がもう1本の細い路地を加えて"七福の辻"に改めたんや。すごい知恵」。
|
 歩くこと3時間。驚き、桃の木、日本書紀まで飛び出した今回の歴史散歩。打ち上げにコリアンタウンで味わった焼肉&ビールの旨さときたら! 歩くこと3時間。驚き、桃の木、日本書紀まで飛び出した今回の歴史散歩。打ち上げにコリアンタウンで味わった焼肉&ビールの旨さときたら! |