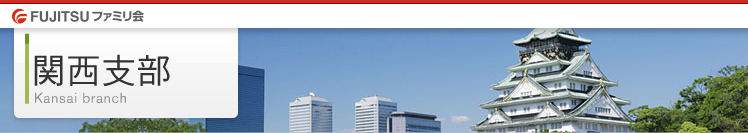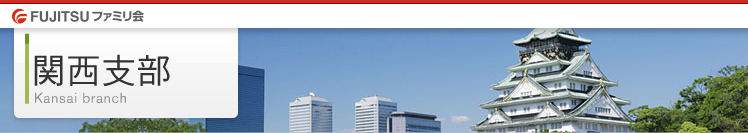|
●口縄坂で女学生との出会いに胸躍らせたオダサク |
 源聖寺坂から松屋町筋を南へ下ると、木々の間に溶け込んだ趣のある坂道が現れる。ここが「口縄(くちなわ)坂」。源聖寺坂と同じく上町台地の坂を代表する坂で、織田作之助の「木の都」の舞台になっている。 源聖寺坂から松屋町筋を南へ下ると、木々の間に溶け込んだ趣のある坂道が現れる。ここが「口縄(くちなわ)坂」。源聖寺坂と同じく上町台地の坂を代表する坂で、織田作之助の「木の都」の舞台になっている。 |
 「口縄とは大坂城築城のとき、縄打ちを始めた場所だからという説もあるけど、泉州弁では、朽ちた縄が蛇に似ているので口縄と言うんやね。つまり、坂道の起伏が蛇に似ているところからこの名が付いたという説が僕は当たっていると思う。かつて心斎橋にあった鰻谷(うなぎだに)の町名も同じ。船場にある道修町(どしょうまち)は、どしょう谷と呼ばれていたんやけど、ドジョウがなまってついたと確信しているんや」。 「口縄とは大坂城築城のとき、縄打ちを始めた場所だからという説もあるけど、泉州弁では、朽ちた縄が蛇に似ているので口縄と言うんやね。つまり、坂道の起伏が蛇に似ているところからこの名が付いたという説が僕は当たっていると思う。かつて心斎橋にあった鰻谷(うなぎだに)の町名も同じ。船場にある道修町(どしょうまち)は、どしょう谷と呼ばれていたんやけど、ドジョウがなまってついたと確信しているんや」。
|
 現在、坂は凹凸なしに改修され、手すりなどもついているが、覆い繁る木々や石畳に昔の面影を残している。 現在、坂は凹凸なしに改修され、手すりなどもついているが、覆い繁る木々や石畳に昔の面影を残している。
|
 坂を登っていくと、夕陽丘かいわいを描いた織田作之助の「木の都」の最終節を刻んだ文学碑が建っている。 坂を登っていくと、夕陽丘かいわいを描いた織田作之助の「木の都」の最終節を刻んだ文学碑が建っている。 |
 「上町台地(上汐町)で育ったオダサクは、この坂に足しげく通ったんやね。この界隈の高津中学(現・高津高校)から京大に進学するんやけど、この坂を通ったのは夕陽丘女学校(現・夕陽丘高校)があったから。女学生見たさに通ったんや。本人が本の中でそう書いているんやから間違いない(笑)」。 「上町台地(上汐町)で育ったオダサクは、この坂に足しげく通ったんやね。この界隈の高津中学(現・高津高校)から京大に進学するんやけど、この坂を通ったのは夕陽丘女学校(現・夕陽丘高校)があったから。女学生見たさに通ったんや。本人が本の中でそう書いているんやから間違いない(笑)」。
|
| 知られざる文豪のエピソード。女学校はその後移転したが、坂の途中に小さな夕陽丘女学校跡の遺跡が立っている。 |
|
| ●夕日が美しいから「夕陽丘」。名付け親は藤原家隆 |
 このあたりの坂は、とりわけ夕陽が美しい。もともと坂は岩盤の上町台地から海岸線に通じる場所に位置し、大阪湾に沈む夕陽が一望できたようだ。夕陽丘という地名も、新古今和歌集の選者、藤原家隆が、上町台地から見える夕陽に感嘆し、詠んだ句からこの地名が付けられたという。その家隆の墓が、口縄坂のすぐ南にある。 このあたりの坂は、とりわけ夕陽が美しい。もともと坂は岩盤の上町台地から海岸線に通じる場所に位置し、大阪湾に沈む夕陽が一望できたようだ。夕陽丘という地名も、新古今和歌集の選者、藤原家隆が、上町台地から見える夕陽に感嘆し、詠んだ句からこの地名が付けられたという。その家隆の墓が、口縄坂のすぐ南にある。 |
 口縄坂から下がって南に進むと大江神社の石段の横にあるのが「愛染坂」だ。下り口坂の横に建つ勝鬘(しょうまん)院愛染堂は、「愛染さん」で親しまれ、聖徳太子が建てたといわれる四天王寺の別院。もともと四天王寺は、「敬田院」「施薬院」「療病院」「悲田院」の4つからなり、このうちの「施薬院」が現在の愛染さんだ。聖徳太子はいろいろな薬草をここに植えて、病気の人に分け与えたといわれる。社会救済事業発祥の地ともいわれる所以。 口縄坂から下がって南に進むと大江神社の石段の横にあるのが「愛染坂」だ。下り口坂の横に建つ勝鬘(しょうまん)院愛染堂は、「愛染さん」で親しまれ、聖徳太子が建てたといわれる四天王寺の別院。もともと四天王寺は、「敬田院」「施薬院」「療病院」「悲田院」の4つからなり、このうちの「施薬院」が現在の愛染さんだ。聖徳太子はいろいろな薬草をここに植えて、病気の人に分け与えたといわれる。社会救済事業発祥の地ともいわれる所以。 |
 その一筋南にある「清水(きよみず)坂」は、坂の上の清水寺にちなんで名づけられた坂。広くてなだらかな石畳の坂の上の高台には京都の清水寺を模してつくった清水の舞台もあり、通天閣などが一望できる。南側のがけから流れ出る玉出の滝は、小さいながら大阪市内唯一の滝として知られ、滝修行をしている人も。 その一筋南にある「清水(きよみず)坂」は、坂の上の清水寺にちなんで名づけられた坂。広くてなだらかな石畳の坂の上の高台には京都の清水寺を模してつくった清水の舞台もあり、通天閣などが一望できる。南側のがけから流れ出る玉出の滝は、小さいながら大阪市内唯一の滝として知られ、滝修行をしている人も。
|
|
|
|
●四天王寺舞楽の演奏家が住んだまち、伶人町 |
 「天神坂」は、そのまま南に下ったところにある石畳のなだらかな坂だ。菅原道真ゆかりの安居天神に通じることからこの名がついた。安居天神には天王寺七名水の1つ、「安井の清水」があるところから、坂の途中にはその湧き水をイメージした小さな井戸のモニュメントがつくられ、さらさらと涼やかな水音を立てている。 「天神坂」は、そのまま南に下ったところにある石畳のなだらかな坂だ。菅原道真ゆかりの安居天神に通じることからこの名がついた。安居天神には天王寺七名水の1つ、「安井の清水」があるところから、坂の途中にはその湧き水をイメージした小さな井戸のモニュメントがつくられ、さらさらと涼やかな水音を立てている。 |
 「清水谷高校のある清水谷町も、上町台地の湧き水に由来するんやね。清水谷は心斎橋の近くにある清水町と上町台地の地下でつながっていて、心斎橋にある風呂屋"清水湯"の起源もここから」。 「清水谷高校のある清水谷町も、上町台地の湧き水に由来するんやね。清水谷は心斎橋の近くにある清水町と上町台地の地下でつながっていて、心斎橋にある風呂屋"清水湯"の起源もここから」。
|
 安居天神の境内には、大坂夏の陣で戦死した真田幸村の碑がある。 安居天神の境内には、大坂夏の陣で戦死した真田幸村の碑がある。 |
 かいわいで天神坂の解説をしていた師匠が「これ、なんて読むか分かる?」と立ち止まった。見れば「伶人町」の町名案内板。 かいわいで天神坂の解説をしていた師匠が「これ、なんて読むか分かる?」と立ち止まった。見れば「伶人町」の町名案内板。
|
 「れいにんちょう、というんやけど。伶人とは、古来の四天王寺舞楽の演奏家のこと。明治維新までここに伶人が住む八人屋敷があったんやね。伶人は明治天皇の東幸とともに東京へ移動して宮内省に配属されたんや。実は君が代を作曲した林広守も、ここ出身。いわば君が代のルーツがここにあるんや。歴史ある町名やねぇ」。 「れいにんちょう、というんやけど。伶人とは、古来の四天王寺舞楽の演奏家のこと。明治維新までここに伶人が住む八人屋敷があったんやね。伶人は明治天皇の東幸とともに東京へ移動して宮内省に配属されたんや。実は君が代を作曲した林広守も、ここ出身。いわば君が代のルーツがここにあるんや。歴史ある町名やねぇ」。
|
| 初めて聞く耳より情報。これぞ大阪人なら絶対押さえておきたい歴史ネタだ。
|
 七坂のいよいよ最後は、松屋町筋の南端と四天王寺西門を結ぶ「逢坂」。現在は国道25号線になっている。 七坂のいよいよ最後は、松屋町筋の南端と四天王寺西門を結ぶ「逢坂」。現在は国道25号線になっている。
|
| 「昔は合坂とも書かれ、坂下の辻を合邦(合法=がっぽう)の辻といって、聖徳太子と物部守屋が仏教を論じ合い、法を並べて比べ合わせたところに由来するんや」。
|
| 昔はかなりの急坂で大坂から大和へ通じる要路だったらしいが、残念ながら、いまは車の往来が激しい幹線道路になっており、昔の面影はない。
|